配送業を始めて、ちょうど半月が過ぎた頃の話だ。まだ慣れない仕事で毎日必死だった俺に、忘れられない体験が待っていた。9月のあの夜の出来事を、今でも鮮明に覚えている。
その日の配達
9月の夕方、いつものように配達ルートを回っていた。その日の荷物の中に、住宅街から離れた田舎の雰囲気のエリアにある家宛のものがあった。
これまで配達したことのない場所で、地図を見ながら「こんなところにも家があるんだな」と思いながら向かった。
特に時間指定もない普通の荷物だった。何の変哲もない、ごく普通の配達のはずだった。
大きな平屋
その家に着いた時、まず目に入ったのは大きめの平屋だった。
田舎の雰囲気に似合った、どっしりとした佇まいの家だ。そして駐車場には、普段は見かけないほど多くの車が停まっている。軽自動車から高級車まで、様々な車種が所狭しと並んでいた。
「何かの集まりかな?」
そう思いながら家を見上げると、窓という窓が全開でリビングは明々と電気で照らされていた。
光に導かれて
インターホンを押すという気持ちより先に、なぜかリビングの光に引き寄せられた。
まるで何かに導かれるように、その明るい方へ足が向いた。
最初に目に入ったのは人の足の裏だった。
その瞬間、なぜか直感的に察した。
「これは…」
黒い服の人たち
顔には白い布がかけられていて、その周りには黒い服を着た人たちが静かに座っていた。
みんな項垂れて、重い空気に包まれている。
遺体の隣では、お母さんと思われる女性が深く項垂れていた。その姿を見た瞬間、胸が締め付けられるような思いになった。
家全体を包む空気は、言葉では表現できないほど重く、悲しみに満ちていた。
荷物の宛名
慌てて手元の荷物を確認した。宛名を見ると、その家の住所で間違いない。そして受取人の名前も…
「まさか」
嫌な予感が頭をよぎった。
リビングの光に寄せられたようにその方向へ向かう。
こちらの車の音と足音で気づいたのか 年配の男性が出てきた。疲れ果てた表情をしていて、目は赤く腫れていた。
「宅急便です」
そう言って荷物を差し出すと、男性は宛名を確認した。
「名前は間違ってないです。が、この荷物はこの子のですが…」
そう言ってご遺体の方を見た。
その声は、深い悲しみに満ちていた。
お父さんは、震える手で荷物を受け取った。
「ありがとうございます」
こちらに気を使ってか微笑んでいたが
そう言った声は、かすれていた。
その後
その日以来、俺はその家の前を通ることはない。
というより、その家への配達がなくなったのだ。亡くなった人だけが荷物を頼んでいたから、もう配達する理由がない。
でも、たとえ他の配達があっても、きっとその道は避けただろう。
あの日見た光景、あの時感じた空気の重さ、お父さんの悲しそうな声、項垂れるお母さんの姿…
全てが今でも鮮明に記憶に残っている。
今思うこと
配達員を始めて半月。人生には本当に色々なことがあるんだと、身をもって実感した出来事だった。
荷物の向こうには、必ず誰かの人生がある。その人の想い、家族の想い、そして時には、もう叶わない想いも。
あの日のことを思い出すたびに、一つ一つの配達の重みを感じている。
この体験をした後、改めて配達という仕事の意味を考えるようになった。ただモノを運ぶだけではない、人と人を繋ぐ大切な仕事なのだと。
📦 業界補足:配達員が直面する“見えない人生”
配達業務は単なる物流の一部として語られがちだが、現場ではこのように「人の人生の節目」に触れる瞬間がある。特に個人宛の荷物は、贈り物、日用品、書籍、医療品…いずれも“その人だけの物語”を抱えている。配達員の心理的ケアやサポート体制の必要性が、今後より注目されるかもしれない。
まとめ
配達という仕事の裏には、人の暮らしがある。誰かが待っている荷物、あるいは、もう届かない荷物。
この出来事をきっかけに、私は“届ける”という行為の重みを強く感じるようになった。
そして今も、配達車の窓から流れる風景の中に、あの夜の静かな光景を思い出すことがある。
関連タグ: #配達員のリアル #忘れられない出来事 #遺族との対面 #仕事の意味
💬 ご意見・ご感想・通報はこちらからどうぞ。
忘れられない出来事、あなたにもありますか?
この体験が何かの気づきになった方は、ぜひコメントをお寄せください。
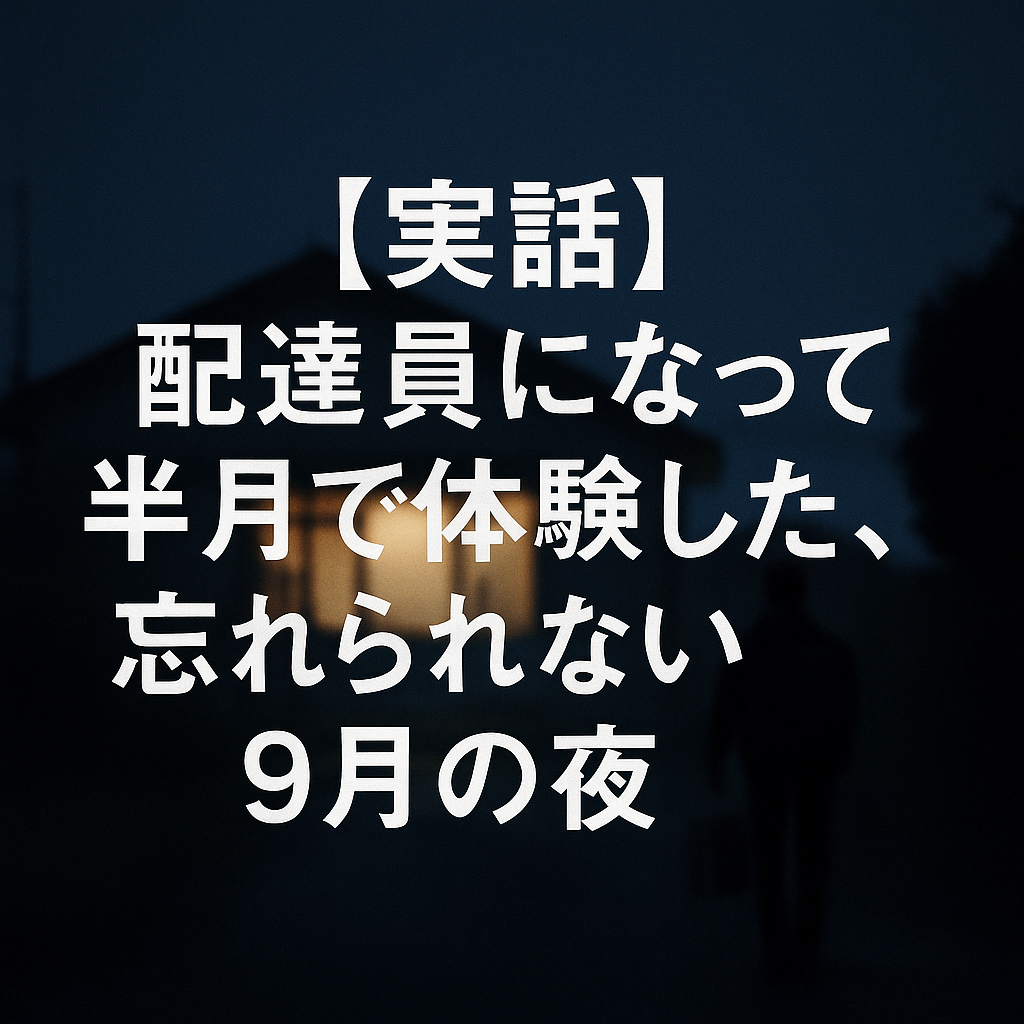
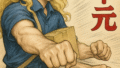
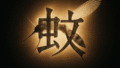
コメント 気になる事等なんでもどうぞ!